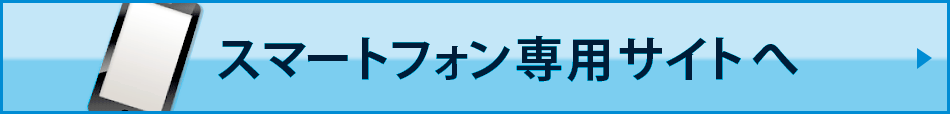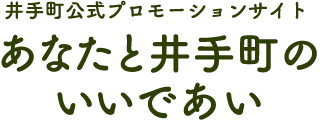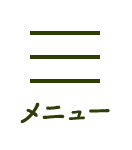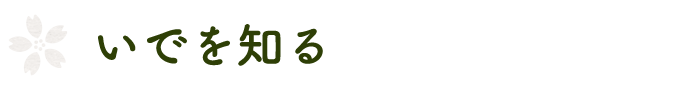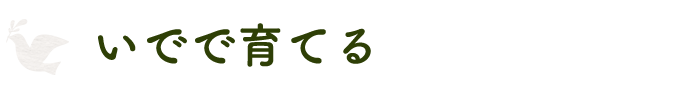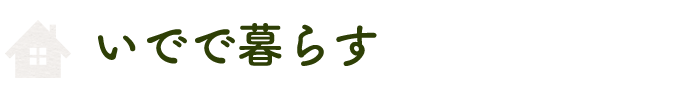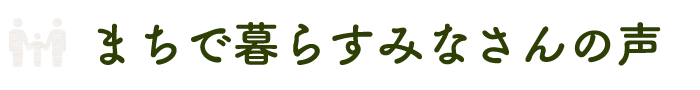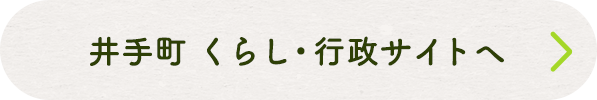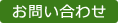井手の歴史に触れる

▲時代絵巻行列の様子 京都と奈良を結ぶ道の中間に位置し、古くから多くの人々が行き交ってきた井手町。町の随所に残された史跡からは、井手の地で長年にわたって紡がれた歴史を伺うことが出来ます。
橘諸兄公旧跡

橘諸兄は、井手寺を建立するなど井手を拠点として活躍した奈良時代政治の要人です。
684年に生まれ、740年に45代聖武天皇を井手の玉井頓宮にまねき、749年には正一位左大臣になったと伝えられています。 また、
「万葉集」の撰者としても知られた文人で、父美努王とともに井手の地を愛し、玉川岸に山吹を植えたといわれています。
井手寺跡

かつて聖武天皇の時代に左大臣を務めた橘諸兄が
橘氏の氏寺として創建したと伝えられる奈良時代の寺院の跡です。今はわずかな史跡にかつての面影を残すのみですが、これまでに行われてきた文献や発掘調査の結果によると約240m四方の広大な寺域があったとされています。
玉津岡神社

上井手地区にある神社で、境内には橘諸兄を祀った
橘神社があります。江戸前期に再建された本殿は京都府の登録文化財にも指定されています。
石橋瓦窯跡

南都七大寺の一つ
大安寺の瓦を生産していた瓦窯跡で、4基の窯跡と灰原が発見されています。平成18年には国の史跡に指定されています。
小野小町塚

六歌仙の一人として知られ、平安時代を代表する女性歌人の
小野小町は、かつて井手にあった井手寺で没したと伝わっています。玉川の山吹を詠んだ歌も残されており、井手と小野小町の縁があったことが伺えます。
左馬ふれあい公園

駒岩の左馬は花崗岩の表面に刻まれた絵馬で、平安時代末期の作と伝わっています。水を司る神であったものが、女芸上達の神として信仰されました。左馬ふれあい公園はそんな駒岩の左馬をご覧いただくことが出来る公園として、山間の川辺に整備されています。
松の下露の碑

元弘元年(1331)に笠置山で挙兵した
後醍醐天皇は、幕府軍に追い詰められ、
大正池近くで捕らわれの身となりました。この松の下露の碑は、玉川沿いにある小さな石碑です。後醍醐天皇が有王の松の下で休まれた際、お供の藤原藤房と交わされた情景を伝えています。
高神社

鎌倉時代成立の「高神社文書」には猿楽奉納の記録があり、日本最初の猿楽に関する記録の一つとされています。
中神琴渓の墓


江戸中期に京都で活躍した漢方医である中神琴渓は、光格天皇を診察したことで田村新田の地を拝領し、晩年を田村新田で過ごしたと伝わっています。今でも有王には墓が残されており、
墓参りをすると願いが叶うと言われています。