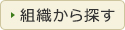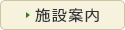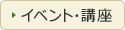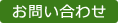令和7年度の介護保険料をお知らせします
介護保険料は、要介護認定者数や訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などの介護サービスがどのくらい必要かなどのサービス見込みをもとに3年ごとに見直しをおこなうことになっています。 ※要介護認定とは、介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者が認定するものであります。 井手町では、高齢者数の増加に伴う介護サービスにかかる費用の増加が引き続いて予想され、財政状況がかなり厳しい状態となる見込みです。もし現在の保険料のままで引き上げずに進むと、今後適正な介護保険事業の運営ができなくなる可能性があり、必要な時に必要な介護サービスを受けることが難しくなります。 将来に安心して介護を受けることができ、健全な介護保険事業が運営できるよう、保険料を引き上げて、皆様にご負担をお願いするものです。 ※令和7年度介護保険料は、令和6年1月~令和6年12月の合計所得金額や、住民税の課税状況に応じて、6月に決定し、6月中旬までに通知します。 ※国の制度により、第1段階~第3段階の対象者に対する保険料軽減措置が設けられます。
所得に応じて16段階の保険料になっています
被保険者の方が納める介護保険料は、毎年4月1日現在の介護保険被保険者の属する世帯の世帯構成に基づき、住民税の課税状況や所得の状況などにより、第1から16段階までのいずれかに決まります。
第1段階
(対象者) 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者(注1)で住民税世帯非課税(注2)の方、住民税世帯非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額の合算額が80.9万円以下の方
・保険料の調整率:基準額×0.285
・年額保険料(単位:円):21,194
第2段階
(対象者) 住民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円以下の方
・保険料の調整率:基準額×0.485
・年額保険料(単位:円):36,067
第3段階
(対象者) 住民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が120万円を超える方
・保険料の調整率:基準額×0.698
・年額保険料(単位:円):51,907
第4段階
(対象者) 本人が住民税非課税者で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80.9万円以下の方
・保険料の調整率:基準額×0.95
・年額保険料(単位:円):70,646
第5段階
(対象者) 本人が住民税非課税の方
・保険料の調整率:基準額×1
・年額保険料(単位:円):74,364
第6段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以下の方
・保険料の調整率:基準額×1.35
・年額保険料(単位:円):100,392
第7段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×1.37
・年額保険料(単位:円):101,879
第8段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×1.62
・年額保険料(単位:円):120,470
第9段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×1.72
・年額保険料(単位:円):127,907
第10段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×1.87
・年額保険料(単位:円):139,061
第11段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×2.30
・年額保険料(単位:円):171,038
第12段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×2.35
・年額保険料(単位:円):174,756
第13段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×2.40
・年額保険料(単位:円):178,474
第14段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が820万円以上920万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×2.45
・年額保険料(単位:円):182,192
第15段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の方
・保険料の調整率:基準額×2.50
・年額保険料(単位:円):185,910
第16段階
(対象者) 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,020万円以上の方
・保険料の調整率:基準額×2.55
・年額保険料(単位:円):189,629
※基準額は、年額74,364円(月額6,197円)
(注1)住民税世帯非課税とは、世帯構成員全員が非課税のことです。
(注2)老齢福祉年金とは、国民年金が発足した1961年(昭和36年)の当時にすでに高齢等であったことを理由に国民年金を受け取ることができない人々を救済するために設けられた制度です。
介護保険料の納め方は2通りあります
介護保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、町が発行する納付書や口座振替により金融機関等でお支払いいただく「普通徴収」があります。
特別徴収
老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円以上の方(月額1万5,000円)以上の方
普通徴収
- 老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円未満の方(月額1万5,000円)未満の方
- 老齢福祉年金のみ受給している方
- 年度の途中で65歳になられた方
- 年度の途中で所得段階が変更になった方
- 年度の途中で他の市町村から転入された方
- 4月1日時点で老齢・退職(基礎)年金等を受けていなかった方
保険料滞納による措置
【1年以上滞納すると】 サービスを利用したときの費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。 【1年6ヶ月以上滞納すると】 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。 【2年以上滞納すると】 サービスを利用するときに利用者負担が3割になったり、高額介護(介護予防)サービス費が受けられなくなったりします。 ※災害など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。
留意事項
第2号被保険者(40歳~64歳)(注3)の方については、加入している医療保険の算定方式に基づき、医療分と介護分を決定し、あわせて医療保険料として納めます。 年金から天引きする特別徴収は、その年度分の介護保険料をその年度内に支給される年金から天引きしますので、結果的に先払い方式で納付いただくこととなっています。 (例 4月支給分の年金は、2,3月分として支払われますが、介護保険料は4、5月分として納付いただいております。) (注3) 第2号被保険者・・・40~64歳の方(医療保険に加入している方)であり加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす疾病(特定疾病(注4))により介護や支援が必要となっとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません。(第1号被保険者・・・65歳以上の方であり、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。) (注4)がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統委縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症